私は月給制(賃金締日は毎月末日)の正社員として勤務しています。会社の雇用条件に不満があるので,転職活動をしていたところ,好条件で採用内定を貰えました。転職先からは平成30年11月1日から勤務してほしいと要請されています。そこで,平成30年10月10日に平成30年10月31日での退職を伝える退職届を提出しました。ところが,会社は就業規則上「退職は最低でも1ヶ月前に退職願を提出し,会社の承認を得なければならない」と定めていることから,退職日を10月31日とすることを承認しませんでした。この場合,退職の効力はいつの時点で発生するのでしょうか?
民法では,2週間の予告期間をおけば、労働者は辞職することができることになっています(民法627条1項)。ただし、期間によって報酬を定めた場合(例えば月給制の場合)には、解約の申し入れは次期以降についてすることができ、当期の前半までに行わなければならないとされています(民法627条2項)。当期の前半に申し入れをした場合は次期以降に、当期の後半に申し入れをした場合は次々期以降に労働契約を終了させることができます。ちょっとわかりにくと思いますので,具体的に解説しましょう。
ご相談のケースでは,月給制で賃金計算期間は毎月1日〜月末までとなっています。そして,10月10日という賃金計算期間の前半に退職の申し出がなされています。この場合,退職の効力は次期の初日である平成30年11月1日に効力が発生します。
ただし,会社が承認する場合は退職時期を早めることは出来ます。
なお,民法による辞職の効力発生期間に関する定めを延長したり,使用者の承認を条件とすることは仮に就業規則に定めがあったとしても効力は有しないと解されます。また,民法が改正され2020年4月1日以降は期間によって報酬を定めている場合であっても2週間の予告期間により退職の効力が生じることになります。
雇用期間が定められていない雇用契約の場合,2週間の予告期間をおけば、労働者はいつでも辞職することができます(民法627条1項)。この場合、辞職の申し入れの日から2週間が経過すれば雇用契約は終了することになります。ただし、期間によって報酬を定めた場合(例えば月給制の場合)には、解約の申し入れは次期以後についてすることができ、当期の前半までに行わなければならないとされています(民法627条2項)。当期の前半に申し入れをした場合は次期以後に、当期の後半に申し入れをした場合は次々期以後に労働契約を終了させることができます。これではわかりにくいと思いますので,以下のとおり図説します。
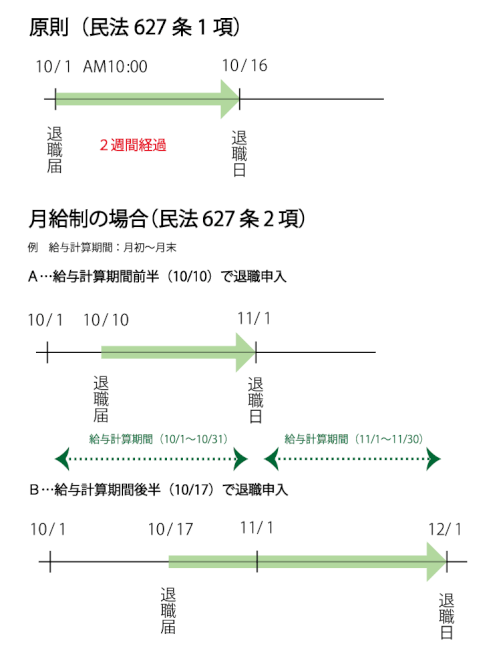
これに対して,雇用期間の定めのある雇用契約(有期雇用)である場合は,労働者は「やむを得ない事由」がある場合でなければ、期間途中で辞職することはできません。また、やむを得ない事由がある場合でも、それが労働者の過失によって生じたもので、使用者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する義務を負います(民法628条)。
ただし、契約期間の初日から1年を経過した後は、いつでも自由に辞職することができることが暫定的に認められています(労基法附則137条 この場合でも、民法627条1項により2週間の予告期間が必要です)。
もっとも、この労基法附則の定めは、一定の事業の完了に必要な期間を定めた場合、専門的知識等を有する労働者および60歳以上の労働者との有期労働契約には適用されませんので注意が必要です。
会社によっては,社員に急に辞職されると困ると考えて,「1カ月前に退職願を提出しなければならない」もしくは「会社の承認を得なければならない」などの定めを就業規則に定めている場合もあります。また,このような定めが無くとも,退職者からの退職の申し出を拒絶することがあります。
しかし,「退職を希望する場合は遅くとも1カ月前に退職願を提出しなければならない」もしくは「会社の承認を得なければならない」などの定めがあり退職を拒絶したとしても,上記1の民法627条の予告期間を置けば辞職の効力は生ずることになります。
民法627条は労働者の退職の自由(職業選択の自由 憲法22条1項)を保障する趣旨の強行規定であり,これに反する就業規則等の規定や処理は無効となると解されています(土田道夫「労働契約法[2版]」632頁~有斐閣)。民法627条について労働者に不利になる態様での辞職の予告期間を延長することは出来ないと解されます(ただし,反対説もあります。)。
労働者が民法627条の予告期間を置かずに退職することを希望し,使用者もそれを了承する場合は,退職の時期を短縮することが出来ます。
例えば,労働者が即日退職を希望した場合,会社が了承するのであれば即日退職の効果が発生します。
平成29年5月26日に成立した民法の一部を改正する法律が,2020年4月1日に施行されます。改正後の民法は,627条1項は維持しつつ,労働者の辞職の自由を保護するとの考えから,同条2項・3項の適用を「使用者からの」解約申入れに限定し,労働者からの解約については,同条1項の規定に従って,2週間前に手続をとることによりいつでも可能であるとしています。
これにより2020年4月1日以降は期間によって報酬を定めている場合であっても2週間の予告期間により退職の効力が生ずることになります。
まずは以下の事実及び証拠を確認してください。
雇用期間の有無,賃金計算期間
【証拠】
□ 雇用契約書
□ 就業規則,賃金規程
退職届の内容
【証拠】
□ 退職届・退職願
□ メール
□ 口頭(録音,記録)
退職届の効力発生時期を見据えて,逆算して退職届を提出しましょう。なお,有給休暇が残っている場合は,それを消化した上で退職することも可能です。
退職の意思表示を行った時期が後々問題になる可能性があるので,出来れば内容証明郵便(配達証明付き)で行う,メールで行う,電話や口頭で行う場合は録音をする,など記録に残る形で行いましょう。
法律が定める予告期間より前に退職したい場合は,会社と退職時期を交渉します。会社が同意すれば予告期間前に退職することも可能です。
なお,会社が退職届の受理を拒否した場合や就業規則の規定を理由に退職を認めない場合であっても,法律が定める予告期間を経過すれば辞職の効力は生じます。つまり,予告期間を置く限りは,辞職の効力の発生の為には会社の同意は必要ありません。
法律が定める時期に退職の効力が生じます。この場合,社会保険の脱退手続き,離職票や源泉徴収票の交付などの手続きを会社に進めてもらいます。会社が拒否する場合は,それぞれの手続きを所管する役所に問い合わせをしましょう。役所から会社へ指導が行われる場合やそもそも会社の手続きを経ずに手続きが進められることがあります。詳細は役所にお問い合わせください。
大阪地判平成10.7.17労働判例750-79
(事案の概要)
Xは,主に自動車貨物運送業を営む株式会社であるYに,平成7年2月に雇用され,主として線状鋼材を運搬,荷積,荷降する業務に従事していた。
しかし,同8年8月26日,Yの常務取締役であるAが,Xに対し,Xの同月23日の言動は,得意先の従業員に暴言を吐き,手洗い場の流し台を破損させるなど,著しく不穏当なものであったとして,1週間の休職処分を申し渡したところ,Xは,「不公平だ。一方的に俺だけが処分されるくらいなら,会社を辞めたるわ。」と言って,Yの事務所を出て行き,その翌日は出社しなかった。
(裁判所の判断)
裁判所は,「原告(筆者注:X)が平成8年8月26日にしたA常務に対する言動を見るに,原告は,「会社を辞めたる。」旨発言し,A常務の制止も聞かず部屋を退出していることから,右原告の言動は,被告(筆者注:Y)に対し,確定的に辞職の意思表示をしたと見る余地がないではない。しかしながら,原告の「会社を辞めたる。」旨の発言は,A常務から休職処分を言い渡されたことに反発してされたもので,仮に被告が右処分を撤回するなどして原告を慰留した場合にまで退職の意思を貫く趣旨であるとは考えられず,A常務も,飛び出して行った原告を引き止めようとしたほか,翌8月27日にもその意思を確認する旨の電話をするなど,原告の右発言を,必ずしも確定的な辞職の意思表示とは受け取っていなかったことが窺われる。したがって,これらの事情を考慮すると,原告の右「会社を辞めたる。」旨の発言は,使用者の態度如何にかかわらず確定的に雇用契約を終了させる旨の意思が客観的に明らかなものではあるとは言い難く,右原告の発言は,辞職の意思表示ではなく,雇用契約の合意解約の申込みであると解すべきである。したがって,右原告の発言が辞職の意思表示であることを前提とする被告の主張は理由がない(なお,念のために付言すると,本件においては,原告は,被告が合意解約の申込みに対する承諾の意思表示をするまでに,右申込みを撤回したというべきであるから,合意解約も成立していないと解される)。」とした。
東京地判昭51.10.29労判264-35
(裁判所の判断)
裁判所は,「法は,労働者が労働契約から脱することを欲する場合にこれを制限する手段となりうるも のを極力排斥して労働者の解約の自由を保障しようとしているものとみられ,このような観点からみるときは,民法第627条の予告期間は,使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である。従って,変更された...規定 は,予告期間の点につき,民法第627条に抵触しない範囲でのみ有効だと解すべく,その限りでは,同条項は合理的なものとして,個々の労働者の同意の有無にかかわらず,適用を妨げられない」と判示した。